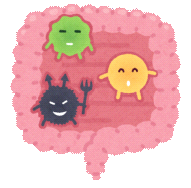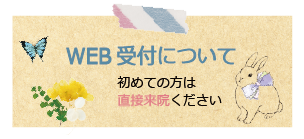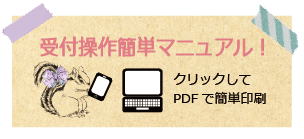ドイツの子供さん2
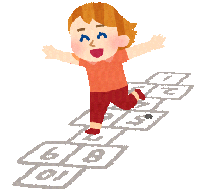
20年~30年前は、小児科医は発熱すれば抗生剤を出すという時代でした。恥ずかしながら私も発熱すれば抗生剤を処方していました。その理由として、乳幼児の細菌感染症は、はじめは普通のかぜなどのウイルス疾患と区別が困難で、時として重篤になること、外来では今日のように少量の血液で、短時間で測定できる検査機器がなく、ウイルス感染症と細菌感染症の区別が困難であったことなどの理由からです。

現在では
①乳児期にヒブワクチン、肺炎球菌ワクチンが定期接種化され、重篤な細菌感染症が著明に減少したこと
②外来で少量の血液検査で、簡単かつ短時間でウイルス感染症と細菌感染症かの推測が可能になったこと
③乳幼児期には数多くのウイルス感染を受けていることが明らかとなり、発熱の多くはかぜなどのウイルス感染症であり、抗生剤を使用しなくても治癒することが多いこと
④かぜなどのウイルス感染症の後に合併することの多い軽度の細菌性中耳炎、副鼻腔炎などは、抗生剤を使用した場合と使用しない場合との比較で治癒期間に差がないこと
などの理由から一般小児科外来で、病初期に直ちに抗生剤を必要とする疾患は多くありません。
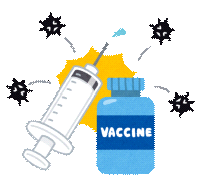
発熱早期に抗生剤を服用し3~4日で解熱した場合、抗生剤の効果があったと思いがちです。でもその多くはウイルス感染症であり抗生剤を内服しなくても治癒することが多いと思われます。発熱があるから、のどが赤いから、黄色い鼻水が出るから(副鼻腔炎:よく見られる普通のかぜは、初期には鼻水が透明でしばらくして黄色となります。医学的に鼻水が主症状のかぜを鼻副鼻腔炎といいます)、中耳炎があるからといっても、抗生剤を内服しなくても治癒する場合が実際は多いのです。

また抗生剤を頻回、長期間にわたり使用すると、鼻、のど、腸の中に多く生息している善玉菌(私たち体の中で悪玉菌が増えないように守ってくれています)が減少し、抗生剤の効きにくい耐性菌を含めた悪玉菌が増加してきます。3歳頃までは腸の中に多種類の善玉菌をより多く保つことが、それ以後の健康に非常に大切である可能性があるとの研究、腸内細菌が安定していない幼少期に抗生剤の長期にわたる投与が、大きくなって難病である潰瘍性大腸炎、クローン病などの腸疾患の発症率を上げているという最近の研究報告もあります。